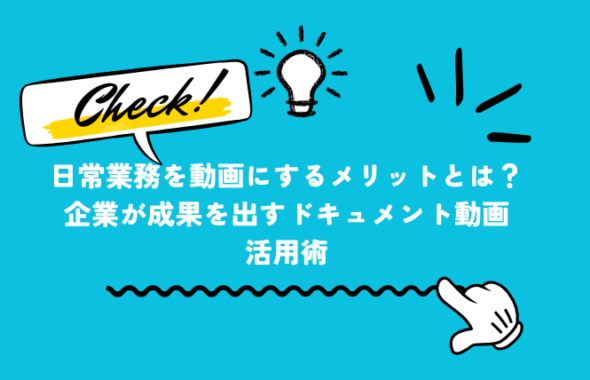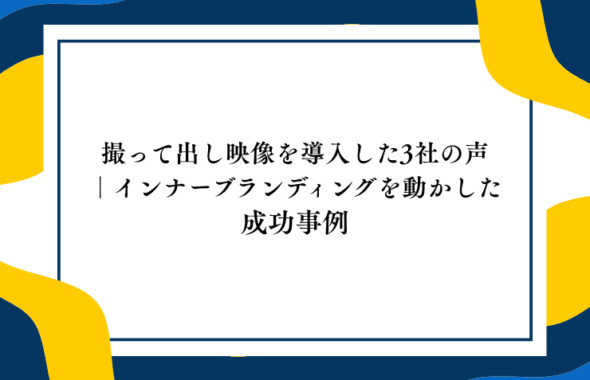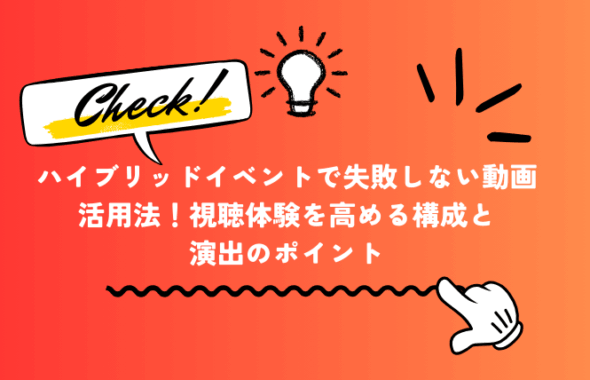撮って出しエンドロールはいらない?──実は 「必要な理由」がはっきりあるんです
1章 なぜ「エンドロールいらない」という声が出るのか
社内イベントの準備を進める中で、必ずと言っていいほど議題に上がるのが「エンドロールは必要か?」という話です。
特に撮って出しとなると「予算が上がる」「当日の運営が大変そう」「そこまでしてやる意味があるのか…?」
という率直な声も多い。これはイベント担当者として、当然の感覚です。映像制作は会場費や演出費に比べると見えづらい価値になりやすく、さらに完成物は“当日にならないとイメージできない”。
そのため、制作経験が少ないほど「なくてもいいのでは?」と思われがちです。
また、一般的なエンドロールのイメージが“映画の最後に流れる名前だけの映像”に引っ張られてしまい、「社内イベントでわざわざ上映しなくても…」と感じる人が多いのも事実です。参加者自身が映り込むわけでもなく、感情移入も起こりにくい。その印象がそのまま、エンドロール=不要な映像という誤解につながってしまいます。
しかし、撮って出しエンドロールは名前の羅列ではありません。参加者の姿、表彰の瞬間、笑った顔、拍手している社員、登壇者の緊張、チームの一体感──本番中に起きた“今日だけの感情”をまとめて映像化する手法です。
“味のないエンドロール”とは本質がまったく違う。ここに多くの担当者が気づいていないギャップがあるのです。
2章 でも実際は…撮って出しエンドロールの満足度は驚くほど高い
GROWSとして現場に立っていて常に感じるのは、撮って出しエンドロールは、視聴率100%の映像だということです。会場の誰もが自分ごととして、食い入るようにスクリーンを見つめる。
SNSやYouTubeのように視聴離脱は一切起きません。それは、映っているのが“自分たちの今日”だからです。
この“今日”という限定性こそ、撮って出しの最大の価値。
表彰で泣いた人、仲間とのハイタッチ、新しいビジョンを聞いて前を向いた顔、その瞬間の熱量は二度と戻ってきません。その“秒で消えてしまう感情”を映像に閉じ込め、最後に全員で振り返ることで会場の空気が一段とまとまる。「ああ、みんなで最高の日を作れたな」と実感が生まれるのです。
さらに、撮って出しには空気を整える力があります。表彰式やキックオフは前半で緊張感が走りやすく、参加者が構えてしまうことがあります。しかし、最後にエンドロールを上映すると、緊張がじわっと溶け、感情が開いた状態でイベントを締められる。これは翌日からの社内コミュニケーションにも影響するほど大きな効果です。
そして、経営層の満足度もとても高い。自社の社員が誇らしげに映り、会社の未来を支える姿が可視化されるから。「これは次の採用でも使いたいね」といった声が現場でよく聞かれます。つまり、エンドロールは「今日のラスト演出」という役割だけでなく、“会社の資産”として活用されるケースも多いのです。
3章:プロが見てきた、あるあるの後悔──「作っておけばよかった…」
これまで数百本の撮って出しエンドロールを制作してきましたが、最も多い声が「こんなに感動するなら、前回も作っておけばよかった…!」という後悔です。特に周年イベントや表彰式では、この傾向が顕著です。
理由は大きく3つあります。
① 表彰者や受賞チームにとって“記念品”の役割を果たすから
社内表彰は多くの場合、社員のキャリアにとって大きな節目です。そこに至るまでの努力、仲間との関係性、普段の働きぶりを象徴する。撮って出しエンドロールは、その日を象徴する映像として“人生の節目の記録”にもなります。「息子に見せました!」と話してくれた受賞者もいます。
② 社員の表情が「社内ブランド資産」になるから
表彰式やキックオフの現場には、普段の仕事中とは違う社員の顔があります。誇らしさ、悔しさ、嬉しさ、チーム愛──その表情は社内広報にとって最も価値がある素材です。写真だけでは伝わらない温度が映像にはある。
③ 一度経験した人ほど価値を理解するから
初めて撮って出しを入れた企業の多くが、翌年以降も継続して制作を依頼されます。「あの感動は必要だ」「イベントの完成度が変わる」と声を揃えて話される。イベントは“積み重ね”だからこそ、1年目の判断が大切なのです。
つまり後悔の多くは、“価値を知らないまま判断してしまう”ことが原因です。この記事を読んでいる担当者さんには、同じ後悔をしてほしくないと思っています。
4章:撮って出しエンドロールが「意味ある映像」になるためのポイント
撮って出しエンドロールは、ただ撮って早く編集すればいいわけではありません。むしろ「当日の現場力」がすべてと言ってもいいほど、繊細な制作です。
ポイントは主に4つです。
① どの瞬間を撮るかを判断する“現場読解力”
ただカメラを回せば良いわけではありません。表彰者が緊張しながら待っている瞬間、仲間が肩に手を置く瞬間、スピーチの余韻──それらを予測しながら撮りに行く必要があります。これは台本通りに動かないリアルな現場だからこそ必要な技術です。
② 社員の表情を丁寧に押さえる“ヒューマンスキル”
社員側が自然に笑ったり、涙がこぼれたりする表情は、声をかけるタイミングや距離感で変わります。カメラマンの空気づくりが映像の質を左右します。
③ 編集テンポと音楽の設計
ただつなぎ合わせるだけではエンドロールは成立しません。1秒単位で“気持ちが乗るテンポ”を作り、音楽とシーンが気持ちよく重なるように微調整していきます。
④ 内製では絶対に出せないプロの品質
スピードとクオリティの両立は熟練度そのものです。GROWSでも、現場ごとにチームを最適化し、編集スタッフが現場内で即編集に入る体制を整えています。これはプロの現場だからこそ成立する工程です。
適当に作ってしまうと「やっぱりエンドロールはいらない」という声が生まれてしまいます。しかし、きちんと設計すると“イベントの完成度”が大きく変わる。ここが本質です。
5章:実例紹介──GROWSの現場で起きている“空気が変わる瞬間”
ここからは、実際のGROWSの現場で起きている“生の変化”を少し紹介します(実名は控えています)。
● 年間表彰式(約1000名規模)
受賞者がステージへ上がる瞬間を追いかけながら撮影し、チーム仲間の涙や拍手を丁寧に集めました。
上映中、会場は完全な静寂。誰もがスクリーンを見つめ、最後のカットで大きな拍手が起きました。
終了後に役員から言われた言葉が「この映像だけで、1年間の成果が全部伝わるね」でした。
● キックオフイベント(約700名)
開始直後は緊張した空気が漂っていましたが、エンドロールで“笑顔のバックステージ”を盛り込み、最後はチームごとに肩を組んでいる人まで。
「来期の雰囲気が一気に良くなった」という声を多くいただきました。
● 周年イベント
創業当時の写真と当日の様子を重ねた構成で制作。「会社の歴史を自分ごと化できた」という声が社員から多く寄せられ、翌年の採用動画にも一部素材が使用されました。
いずれの現場でも感じるのは、撮って出しエンドロールが流れた瞬間に“会場の空気”が変わるということ。
これは照明や音楽だけでは作れない、人の感情の動きに寄り添う映像だからこそ起きる変化です。
6章:まとめ──「いらない?」と迷ったときこそ、入れる価値がある
撮って出しエンドロールは、決しておまけの映像ではありません。
イベントという一日のストーリーを締める、最も感情が動く瞬間を作る演出です。
そして、迷うのは価値を“まだ体験していないからこそ”。
一度でも経験した企業は、ほぼ全て翌年以降も継続されます。
- 今日の熱量を残せる
- 社員同士の一体感が高まる
- 表彰者にとって人生の記録になる
- 経営メッセージを感情で理解できる
- 社内広報・採用にも資産として活用できる
迷ったときこそ、ぜひ一歩踏み出してほしいと思います。
撮って出しエンドロールは、イベントの価値を一段上げる力を持った映像です。