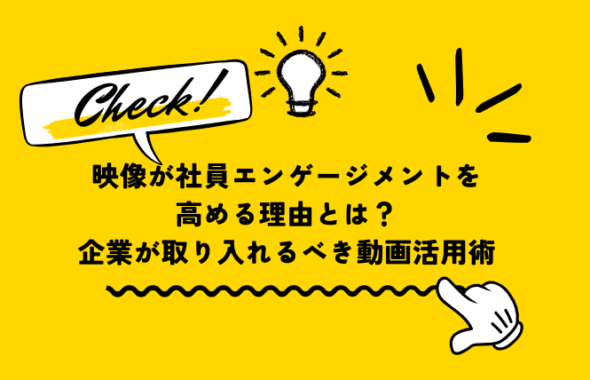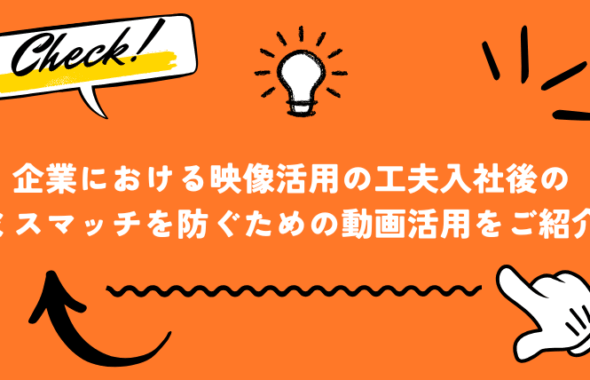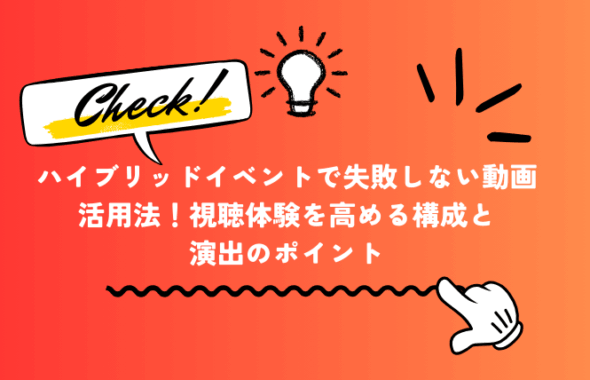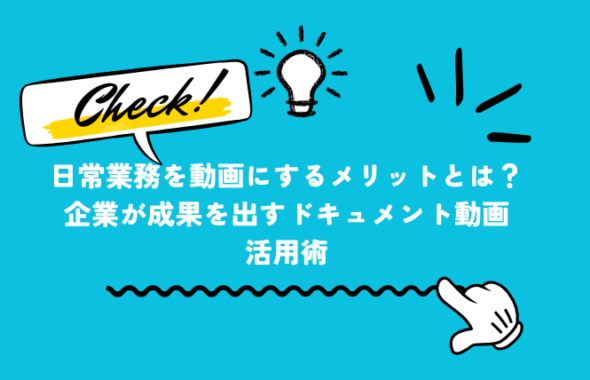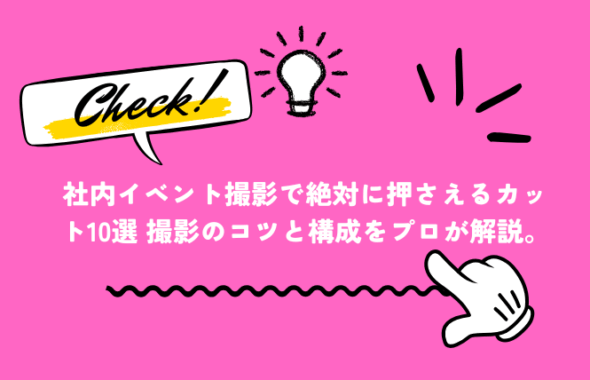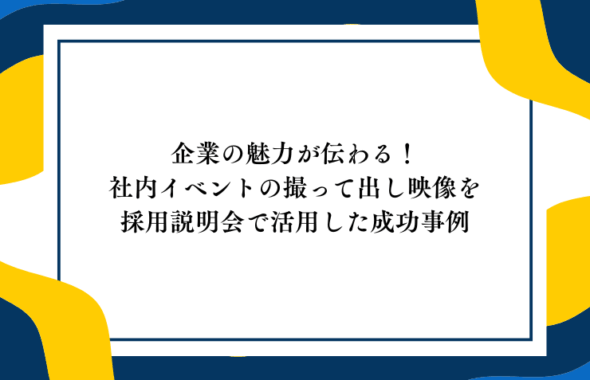企業の魅力が自然と伝わる社内イベント撮って出し映像活用事例
社内イベントを撮影した撮って出し映像を会社説明会で上映したところ、学生の反応が大きく変わり、選考へ進む人数が増えた企業の事例をご紹介します。特別な演出をしていないからこそ、社員の表情や会社の空気がそのまま伝わり、社風理解が深まったことが成果につながりました。本記事では、映像を採用で活用するまでの流れや学生の具体的な反応、実際に数字として現れた効果を詳しく解説します。
1章:社内イベントの映像を見た瞬間に気づいた変化
社内イベントの撮って出し映像を社内で共有した時、採用担当のBさんは思わず手を止めたそうです。特別な演出をしているわけではなく、ただ当日の様子を追いかけた映像でしたが、そこには普段の業務中では見せない社員の表情や、自然な会話の空気がそのまま映っていました。
表彰された社員に仲間が駆け寄って肩をたたく姿。発表を終えて安堵したように笑う瞬間。準備に走り回る裏方メンバーの真剣な眼差し。どのシーンも飾り気がなく、会社の文化そのものが滲み出ていました。
Bさんは、普段採用説明会で学生に企業文化を伝える際、どうしても言葉に頼りがちで、説明が抽象的になってしまうことに課題を感じていました。しかし、この映像を見た時、言葉ではなく空気感で伝わるものが確かにあると気づいたといいます。社員同士の距離感や、イベントの一体感はスライド資料では絶対に伝えきれません。
もともとは社内イベントの雰囲気を残すためだけに撮影した映像でしたが、そこに予想を超える価値を感じる瞬間でした。採用のために作った映像ではなかったからこそ、かえって自然で、学生にも伝わるのではないかという期待が生まれたといいます。
2章:採用説明会への転用を決めるまでの社内の動き
社内イベントの映像を見た後、Bさんはすぐに採用チームのメンバーへ共有しました。映像を見たメンバーからは、言葉よりも伝わるという声が多く上がり、すぐに採用説明会への活用が話題に上りました。特に、社内の一体感や社員同士の関係の良さは日常業務の中ではなかなか見せられない部分で、多くの人がその価値に気づいたと言います。
採用チームには以前から、学生に社風が伝わりづらいという課題がありました。制度や働き方を説明しても、その企業がどんな空気を持っているのか、どんな人が働いているのかがなかなか伝わらない。その壁を越えるためには、言葉ではなく体験に近い情報が必要だと感じていました。
そんな中で見た撮って出し映像の持つ力が、採用課題と自然に結びついたのです。社員の立ち居振る舞いや表情は作れません。また、イベントの熱量はスライドでは再現できません。この映像があれば、説明会の冒頭で学生の心を開くきっかけになるのではないかとBさんは考えました。
最終的には、採用チーム全体の賛同を得て、次の説明会で試験的に上映することが決定しました。準備した採用動画ではなく、社内イベントのリアルが学生にどう届くのか。その反応を確かめたいという前向きな雰囲気でした。
3章:説明会で上映した当日の様子と学生の反応
説明会当日、撮って出し映像を流すタイミングになると、会場は一瞬静まり返りました。スクリーンが明るくなると、映像の中で社員たちが動き、笑い、拍手し、イベントの空気がそのまま会場に流れ込むようでした。学生たちは資料説明の時とは違う集中した目つきで映像を見つめ、少し体を前に乗り出している姿も見られました。
特に印象的だったのは、社員が仲間を称えるシーンで学生たちが小さく頷いていたことです。説明会で企業文化を伝えると頷いてくれることはあまりなかったため、Bさんはその反応を見て驚いたと話します。また、イベントの裏側で支える社員のシーンでは、学生たちの表情が和らぎ、安心したような空気も感じられました。
映像が終わった後の質疑応答では、普段と明らかに質問の質が変わりました。働く人の雰囲気、チームの関わり方、イベントの意図など、より具体的で深い質問が増えました。学生自身が映像から企業を感じ取り、自ら興味を持って掘り下げようとしている様子がはっきりと見て取れたのです。
映像を流したことで説明会の空気が柔らかくなり、企業との距離が縮まった瞬間でした。
4章:説明会後に見えた数字の変化と担当者の実感
説明会後のアンケートでは、映像の印象が強く残ったという回答が多く寄せられました。特に、会社の雰囲気が伝わった、働く人の表情が印象的だったという声が目立ちました。学生が企業に対して親近感を持てたことが、次の行動につながったのではないかとBさんは分析しています。
さらに、一次選考への進行率がこれまでよりも高い結果となりました。これまで離脱していた層が残り「もっと知りたい」という姿勢が強くなったことが数字に表れたのです。説明会だけでは伝わらない、社員の温度や現場での関係性が、学生の安心感につながったと考えられます。
Bさんは、映像だからこそ伝わる情報があると改めて実感したそうです。制度や特徴を説明しても、自分の未来をイメージできなければ学生は動きません。撮って出し映像は、企業の空気を即座に感じてもらえるため、学生が「自分がここで働く姿」を自然に重ねやすいのだと考えたと話します。
数字の変化は偶然ではなく、映像が心の距離を縮めた結果だと確信できる出来事でした。
5章:リアルな社員の姿がブランド価値として機能した理由
撮って出し映像が採用ブランディングに繋がった理由は、そのままの姿を映しているからだと言えます。イベント中の高揚感、緊張、仲間への思いやりなどは作ることができません。そして、その自然な姿が企業として最も信頼される情報になります。
学生は企業文化を理解するとき、言葉よりも雰囲気で判断します。どんな人が働いているのか、どれだけ真剣に取り組んでいるのか、互いにどう関わっているか。これらは文章では限界があります。一方、撮って出し映像はその空気をそのまま伝えます。
また、社内イベントは企業の価値観が強く表れる場です。成功を讃える風土、挑戦を祝う文化、チームとしての一体感。これらが何よりのブランディングとなり、学生に強い印象を残します。
企業が語るブランドではなく、社員の姿から滲み出るブランド。それが今回の事例の大きな成果につながったと言えます。
6章:採用で撮って出し映像を活用するためのポイント
撮って出し映像を採用で活用する際には、いくつかのポイントがあります。まず、撮影するイベントは、社員の感情が動く場を選ぶことです。表彰式やキックオフミーティングは特に効果的で、自然な姿が映りやすい傾向があります。
映像の長さは三から五分程度が適切です。学生が集中して見ることができ、説明会の進行に負担がありません。また、最初に上映すると場が和らぎ、学生の緊張が取れるという効果もあります。
編集では過度な演出を避け、リアルさを大切にします。ナレーションも最小限にし、社員の表情や行動が語ってくれる構成が理想です。
さらに、採用チーム内で映像の意図を共有し、説明会後の質問に対応できるよう準備しておくと効果が高まります。
7章:まとめ
今回の事例では、社内イベントの記録として撮影した映像が、採用ブランディングの強力な素材となりました。社員の自然な姿は、言葉では伝わらない企業文化を学生に届ける力があります。採用担当者のBさんが実感したように、企業の魅力は特別な演出ではなく、日常の延長にこそ詰まっています。
説明会で上映したことで学生の反応が変わり、質疑応答が活発になり、選考への進行率も向上しました。これは、企業と学生の間にある距離を映像が縮めてくれた結果です。
撮って出し映像は、企業のリアルを最も自然に伝える手段です。社内イベントの空気や社員の表情は、企業の理念や言葉以上にブランドを形作ります。今後、多くの企業でこうした映像活用が採用活動のスタンダードになっていくでしょう。